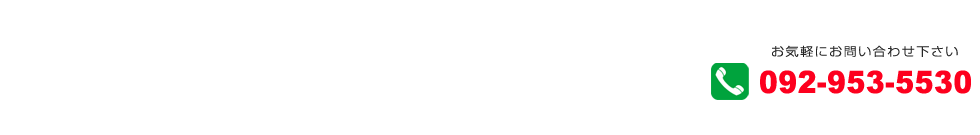コッコレが提供する支援の内容

環境への適応を促すと同時に、そこで必要な動きを獲得することを目指します。

|
立つ・座る・バランスを取るといった動きの中で、自分の身体をコントロールする力を育てていきます。
子どもが環境に適応していくためには、まず自分の身体を思い通りに動かせることが大切です。
身体の発達は、立つ・歩くなどの粗大運動から、手先を使う微細運動へと順を追って育まれます。
トランポリンや平均台などで体幹を鍛える運動とともに、シール貼りやはさみの活動を通して、
目と手の協応(視覚と手の連動)の力も養っていきます。 |

|
子ども自身が自分の身体や生活に気づき、整える力を育むことです。
着替えや靴の脱ぎ履き、身だしなみなどの日常生活動作(ADL)を通して、
自分のことを自分で行う意欲と習慣を育てます。
指先の機能を高める活動では、3指でのつまみ持ちや道具の操作がスムーズにできるよう支援し、
箸や鉛筆の操作へとつなげて いきます。
また、社会の中で自分がどう振る舞うかを考える力も、
SST (ソーシャルスキルトレーニング)を通じて身につけていきます。 |

|
子どもが安心して活動に取り組めるように、
身の回りの環境や活動の流れをわかりやすく整えることを大切にしています。
特にASD (自閉スペクトラム症)のお子様は、一日の流れを視覚的に伝えることで、
見通しを持って落ち着いて過ごせるようになります。
絵カードや写真、スケジュール表などを活用して環境を構造化(TEACCHアプローチ)し、
言葉と視覚情報の両方を使って、理解しやすく伝える工夫をしています。 |

|
体幹の安定を土台に、五感(視覚・触覚・前庭感覚・固有受容感覚など)への働きかけを通じて、
身体全体の協調性を高めていきます。
トランポリンやバランスポールなどの活動を通して、前庭覚や固有受容覚を育て、
姿勢保持や動作のコントロール力を促します。
また、目と手の協応動作(手を見て動かす力)を育む遊びや、
動物模倣運動(くま歩き・ワニ歩きなど)を取り入れることで、楽しみながら身体の調整力を身につけていきます。 |
-
-

- 人は、目・耳・鼻・口・皮ふの"五感"に加えて、「身体の動きや力の入り具合を感じる感覚(固有受容覚)」や 「バランスを保つ感覚(前庭覚)」など、 合わせて7つの感覚を使いながら、周りの世界を認識しています。 こうした感覚がうまく働くことで、記憶したり、想像したり、考えたりする力が育まれていきます。 コッコレでは、子ども一人ひとりの発達段階に合わせて、さまざまな感覚教具や道具を用いた活動を行っています。 楽しみながら感覚を刺激し、感覚と脳のつながりを育てることで、「知ることの楽しさ」や「感じる力」を引き出し、 子どもたちの“知性の目覚め"につなげていきます。
-
-
-

- 言葉を使って人と気持ちを伝え合うためには、語彙を増やすだけでなく、 言葉を発するための身体の土台づくりも大切です。 発語は、舌や唇、口のまわりの筋肉が細かく連動して動くことで生まれます。 また、安定した姿勢や呼吸のコントロールも、はっきりと声を出すためには欠かせません。 コッコレでは、こうした身体づくりを大切にしながら、発達段階に応じた実物や絵カードなどを使い、 繰り返しの言葉かけややりとりの遊びを通して、子どもが「伝わる楽しさ」を感じられるよう支援しています。 楽しみながら語彙力を高め、コミュニケーションの基礎を育んでいきます。
-